このページの目次
1 労働トラブルの類型
近時、職場において以下のような原因で労働トラブルが発生しがちです。
(1)長時間労働・過重労働
労働時間が法定を超える、または休息が十分に取れないことにより、従業員が心身の健康を害するケースがあります。特に「サービス残業(未払い残業)」や「36協定の上限超過」などが問題視されています。
例えば、定時退社を求められるが、実質は自宅で仕事を続けさせるなど、従業員が望まない長時間の残業を強要するなどです。
(2)ハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラなど)
職場での上下関係や人間関係を背景として従業員に精神的・身体的苦痛が生じるケースがあります。最近ではパワーハラスメント(上司による人格否定や過度な叱責)が特に多く、社内外からの通報が増加しています。
例えば、上司が部下のミスに対して必要以上に叱責したり、人格批判をするなどです。
(3)不当解雇・雇い止め
正当な理由なく従業員を解雇したり、契約社員の契約更新を打ち切ったりするケースで、企業の経営状況の悪化を理由に、手続きや説明が不十分なまま解雇するようなケースがしばしば問題となります。
例えば、「勤務態度が悪い」といった曖昧な理由で即時解雇したり、派遣社員や契約社員の一方的な雇い止めが問題になりがちです。
(4)労働条件の不利益変更・曖昧な雇用契約
就業規則や契約内容を労働者の同意なく変更したり、最初から曖昧な条件で雇い入れられたりすることで、労働者が不利益を被るケースが問題視されています。
例えば、出張手当や交通費を一方的に削減したり、雇用形態が「正社員登用前提」と言われていたにもかかわらず、実現されないケースなどです。
(5)メンタルヘルス問題と安全配慮義務違反
職場のストレスや人間関係に起因するうつ病など精神疾患の発症が増加しがちです。企業が適切なケアや環境整備を行わなければ、安全配慮義務違反とされることがあります。
例えば、ハラスメントによりうつ病発症し、労災申請を検討している従業員が、産業医との面談を希望しても応じてもらえないような場合、大きな問題に発展しがちです。
2 労働トラブル発生の背景
こうした労働トラブル発生の背景には、労働生産性向上に対するプレッシャーや、経営者を含む構成員全員の方の理解不足があると考えられます。
前者に関しては、外部期限の厳守は必達目標であるため、労働法規を無視した強引なオペレーションが行われがちであることや、賃上げを実現するために、作業時間を短縮して労働生産性を向上させなければならないといった事情があり、これが個々の従業員に対する大きなプレッシャーになっている事が挙げられます。
後者に関しては、日本の労働法規はかなり労働者側に有利な内容となっていますが、これを理解せずに職場の力関係で強引に事を進めがちな点が挙げられます。経営者による解雇事案だけでなく、上司や同僚によるハラスメントを通じた事実上の退職勧奨も問題となっており、企業全体として労働法規の理解促進が必要とされています。
3 労務トラブル対応は顧問弁護士に丸投げするのが最も手堅いこれだけの理由
(1)労働問題は労働の専門家に任せるのが確実
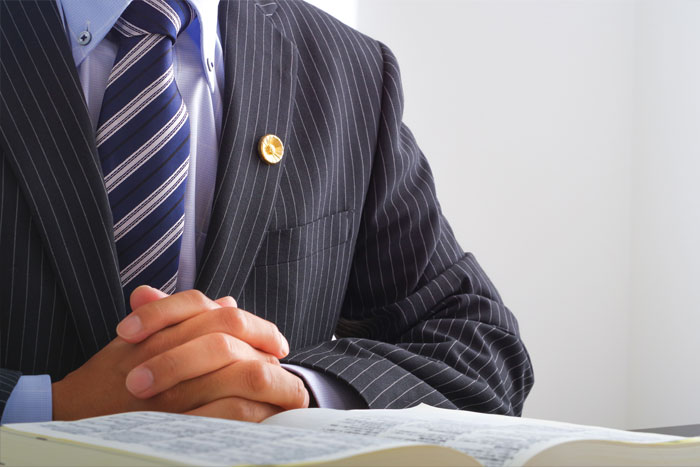
日本の労働法規は被用者側にかなり有利に作られているため、雇用者側の理想や、感情的な対応などは、裁判所ではまず採用されません。
そこで、労働法規の専門家である弁護士に労働トラブル対応は全面的に任せるのが効率的です。
弁護士に依頼すると何が変わるかと言うと、法律や判例を分析して、「このまま進んだ場合の訴訟の結末」を予測し、これを少しでも企業に有利になるよう、話し合いでの落としどころを的確に設定することができます。
こうして設定したギリギリの落としどころに誘導するに当たり、相手も弁護士相手であると腰がひけることもありますし、相手が強引に自らの主張を押し通そうとすると、裁判官の心象がどんどん悪くなるよう、計画的に物事を進めることができます。
こうして、労働トラブルは、訴訟の結末を先読みして、少しでも企業に有利な落としどころに向かわせることのできる顧問弁護士に丸投げするのが最も手堅いのです。
(2)労働審判や損害賠償請求など、法廷紛争に発展しやすい
労働トラブルは、相手に対して「ゼロ回答」をすると、労働審判や損害賠償請求など、法廷紛争に発展しやすいです。これは、当センター長も弁護士会で被用者側の労働相談を多数経験した経験があるため実感していることですが、不満を抱えた被用者が行きつく先は弁護士会であり、弁護士会は弱者救済を強く打ち出すため、法廷紛争を助言しがちです。
こうして、労働トラブルは放置するといずれ法廷紛争に発展する可能性が高いため、早めに顧問弁護士に相談して対処するのが望ましいです。
(3)風評被害が発生するとその被害の回復が難しくなるケースもある
例えば、職場でセクハラを受けたことを上司に相談したが、そのセクハラ行為を隠ぺいされて、かえって二次被害を受けたという従業員がいたら、次に何をするでしょう?
- SNSで企業の悪口を書く
- 週刊誌に被害事実を売り込む
などの対応が予想されます。こうした対応をされると、企業の信用失墜は予想以上に大きく、かつ、回復が困難で、この段階に至ってから弁護士に相談しても対応できる範囲は限られています。
そうではなく、最初から顧問弁護士に相談していおけば、SNSや週刊誌に接触される前に対処することができます。このような「被害予防」の観点からも、早めに顧問弁護士に相談して対処するのが望ましいです。
4 当センターの活用をお勧めするさらなるメリット
当センター長は、京大でMBAを取得して経営を熟知しているほか、官公庁での労務管理やクレーマー対応の経験も豊富で、
- ややこしい相手をいなす
- 企業に必要な「人財」を活用して伸ばす
ことを得意としています。また、法律・会計の両側面から1つの労務トラブルが企業活動全体に及ぼし得るリスクを正確に検知し、先手を打つ助言をすることができます。
労務トラブル対応を任せる顧問弁護士をお探しの企業は、是非、当センターにお気軽にご相談ください。





