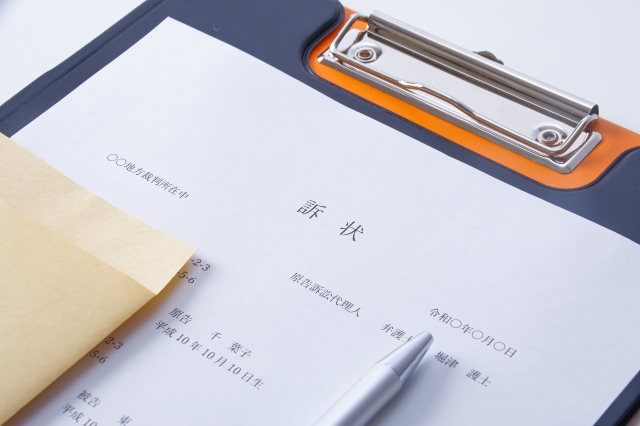
このページの目次
債権回収の最終手段が訴訟提起
企業は日々の経済活動において、多様な取引を通じて数多くの債権を有することになります。通常、取引先は契約や請求書に基づいて支払期限を守り、適切に代金を支払います。なぜなら、支払いを怠れば信用を失い、今後の取引継続に大きな悪影響を及ぼすためです。企業活動における信用は資金力と並んで重要な経営資源であるため、ほとんどの取引先は期限を守り、債権者がわざわざ取り立てに動く必要はありません。
しかしながら、すべての取引が円滑に進むわけではありません。例えば、相手先企業の財務状況が悪化し、資金繰りが困難となる場合があります。その場合、資金を確保するために支払いを後回しにする、あるいは意図的に支払いを拒むという行為が発生することもあります。また、ときには経営者や担当者の感情的な理由、つまり取引内容への不満や過去のトラブルを理由に、合理的な根拠なく支払いを拒否することもあります。こうした状況に直面すると、通常の交渉や請求書の再送付だけでは解決が困難です。
このような場合、債権者が最後の手段として検討するのが「訴訟提起」です。訴訟は裁判所という公的機関を通じて法的に相手の支払い義務を確認し、必要に応じて強制力を行使できるようにするための制度です。ただし、訴訟は一方的に有利なものではありません。確かに法的拘束力を得られるという大きなメリットがありますが、その一方で時間や費用、そして精神的な負担といったデメリットも存在します。したがって、安易に「訴訟をすれば必ず回収できる」と考えるのは誤りです。
そこで本稿では、この訴訟提起という最終手段について、そのメリットと注意点を整理し、債権回収の実務において検討すべきポイントを解説していきます。
強制執行が可能になる
訴訟を提起して勝訴判決を得る、あるいは裁判上の和解に至った場合、債権者は「強制執行」という法的手段を利用できるようになります。これは、債務者が自発的に支払わない場合でも、裁判所の手続きを通じて相手の財産を差し押さえ、回収することが可能となる制度です。例えば、銀行口座の預貯金を差し押さえれば、そこから直接回収することができます。また、不動産や動産といった資産についても差し押さえの対象となり得ます。
債務者にとって、強制執行は大きな脅威です。預貯金が差し押さえられれば運転資金や生活費が不足し、事業や生活の継続に重大な支障をきたします。そのため、多くの債務者は強制執行に至る前に自発的な支払いを選択する傾向があります。つまり、債権者にとって訴訟提起は「強制執行が可能になる」という直接的な効果と同時に、「支払いを促す強力なプレッシャー」としても機能します。
もっとも、強制執行は万能ではありません。手続きには時間と費用がかかり、また差し押さえ対象となる財産が存在しない場合は実効性を欠きます。特に、債務者に資産が乏しい場合やすでに他の債権者による差し押さえが行われている場合には、満額回収が難しくなることもあります。そのため、強制執行は単なる回収手段としてではなく、債務者に対する交渉材料としての性格も強いといえるでしょう。
現実的には、債権者が強制執行の準備を進めつつ、債務者に自発的な支払いを促す形が多く見られます。訴訟によって裁判所のお墨付きを得ること自体が債務者にとって重い心理的負担となるため、支払いに向かわせる強力なカードとなるのです。
消滅時効対策
債権には「消滅時効」という制度が存在し、一定期間が経過すると債務者が「時効を援用する」と主張することで、債権者は回収を求められなくなります。一般的に商取引における債権は5年で消滅時効にかかることが多く、長年支払いが滞っている債権を放置すれば、最終的に回収の可能性が完全に失われる危険があります。
このような事態を防ぐために有効なのが、訴訟提起です。訴訟を起こすと、時効の進行が中断され、判決や和解によって新たな債務名義が確定します。これにより、債権の効力が維持され、長期にわたって回収の可能性を残すことができます。債権者にとっては、たとえすぐに現金を回収できなくとも、「債務は消えない」という状態を確保できることが大きな意味を持ちます。
さらに、訴訟提起は債務者に対して「支払いを逃さない」という強い意思表示にもなります。長期間の放置によって債務者が「もう請求されないだろう」と油断している場合、突然の訴訟は強烈なリマインド効果を生みます。これにより、債務者が和解に応じる、あるいは分割払いを申し出るなど、現実的な解決につながることも少なくありません。
もちろん、訴訟提起が必ずしも即時の回収につながるわけではありませんが、時効の完成を防ぎ、債権を法的に維持する手段としては極めて有効です。特に、古い債権であっても将来的に回収の見込みがある場合には、訴訟による時効中断を検討する価値が十分にあります。
費用対効果
訴訟提起には、避けて通れないコストが伴います。まず、裁判所に対しては収入印紙を納付する必要があり、その額は請求金額に応じて変動します。さらに、郵券(郵便切手)を納めて相手方への書類送達費用を負担しなければなりません。これらは手続き上の必須費用です。
また、訴訟が争いになる可能性がある場合、弁護士に依頼するのが通常です。弁護士費用には着手金や報酬金のほか、実費が含まれ、請求額や事件の難易度に応じて相当な金額になることがあります。加えて、訴訟を提起したからといって必ずしも勝訴できるわけではなく、勝訴判決を得ても相手に資産がなければ回収できないという現実もあります。
さらに、強制執行を行う場合には、別途手続き費用が発生します。例えば、不動産の差し押さえや競売手続きには相応の費用がかかり、預貯金差し押さえでも一定の手続的支出が必要です。つまり、訴訟から強制執行に至るまでには複数の段階で費用が積み重なり、必ずしも回収額がそれを上回るとは限りません。
したがって、訴訟提起を検討する際には、見込まれる回収額と必要な費用を比較し、費用対効果を冷静に分析することが重要です。特に、少額の債権であるにもかかわらず多額の費用を投じてしまうと、最終的に赤字となるおそれもあります。訴訟は「勝てばよい」というものではなく、「回収して利益が残るか」という観点から判断する必要があるのです。
見通しとバランス
訴訟提起を現実に検討する際には、まず相手の財務状況を可能な範囲で調査することが欠かせません。金融機関との取引状況や不動産の所有状況、商業登記簿や官報公告などから、債務者がどの程度の資産を保有しているか、回収の見込みがあるかを推測することができます。債務者に資産がなければ、たとえ勝訴しても回収できず、費用倒れになる危険が高まります。
次に、訴訟提起にかかる費用を概算し、どの程度の資金的負担が発生するかを見積もります。裁判所に納める収入印紙や郵券に加え、弁護士に依頼する場合の費用も加味する必要があります。これらの支出と見込まれる回収額を照らし合わせ、費用対効果が見合うかを検討することが重要です。
さらに、訴訟を行うか否かの判断にあたっては、時間的コストや心理的負担も無視できません。裁判は数か月から数年に及ぶこともあり、その間に経営資源を割く必要が生じます。これらの負担が事業全体に与える影響を冷静に考慮することが求められます。
訴訟提起は、あくまでも数ある回収手段のひとつにすぎません。「必ず訴訟すべき」と決めつけるのではなく、相手の資産状況や訴訟費用、自社の経営状況を総合的に判断し、バランスよく柔軟に対応することが肝要です。場合によっては交渉や分割払いの合意で十分な成果を得られることもあります。重要なのは、訴訟を「目的」とせず、「回収を最大化するための手段」と位置づけることです。
まとめ
債権回収における訴訟提起は、取引先が支払いを拒む場合に選択される最終手段です。訴訟を行えば、勝訴判決や和解によって強制執行が可能となり、相手に大きなプレッシャーを与えられます。また、時効の完成を阻止し、債権を維持するための有効な手段としても活用できます。しかし一方で、訴訟には費用や時間、心理的な負担が伴い、必ずしも回収が保証されるわけではありません。
したがって、訴訟提起を検討する際には、相手の財務状況や見込まれる回収額、必要な費用を慎重に分析することが不可欠です。そのうえで、費用対効果を見極め、訴訟以外の方法も含めて柔軟に判断する姿勢が求められます。重要なのは「訴訟をすること自体」ではなく、「最終的に債権を回収し、経営に資する成果を得ること」であるといえるでしょう。
当センターでは弁護士兼公認会計士が相手の財務状況をふまえて御社に少しでも有利な方策を徹底的に考え抜いてご提案させていただきます。下記よりお気軽にご相談ください。

当センターは、弁護士・公認会計士・中小企業診断士・CFP®・ITストラテジストなどの資格を持つセンター長・杉本智則が所属する法律事務所を中心に運営しています。他の事務所との連携ではなく、ひとつの窓口で対応できる体制を整えており、複雑な問題でも丁寧に整理しながら対応いたします。
窓口を一本化しているため、複数の専門家に繰り返し説明する必要がなく、手間や時間を省きながら、無駄のないスムーズなサポートをご提供できるのが特長です。
大阪府を拠点に、東京、神奈川、愛知、福岡など幅広い地域のご相談に対応しており、オンラインでのご相談(全世界対応)も可能です。地域に根ざした対応と、柔軟なサポート体制で、皆さまのお悩みに親身にお応えいたします。
初回相談は無料、事前予約で夜間休日の相談にも対応可能です。どうぞお気軽にご相談ください。





