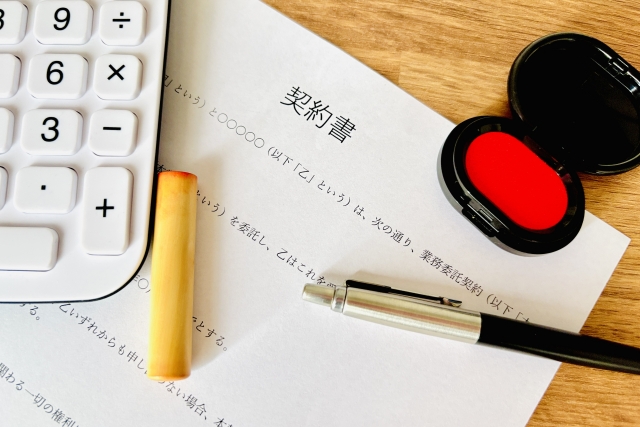
このページの目次
お金のない企業が最強だと言われるが・・
経済社会においては、「お金のない企業が最強だ」と皮肉交じりに語られることがあります。これは、取引先に債務不履行が生じても、そもそも資金が存在しなければ回収のしようがないという現実を指しています。法的に請求権を持っていても、差し押さえられる財産や口座に資金がなければ、実際の回収は不可能に近いからです。その意味では、資金力のない企業に対しては債権者が泣き寝入りせざるを得ないケースが一定数存在しています。
しかし、だからといって本当に回収の道が閉ざされているわけではありません。企業が活動を続けている以上、最低限のキャッシュフローは存在しているはずです。従業員への給与支払い、仕入代金の支払い、光熱費や通信費の支出など、日常的な資金の出入りがなければ事業そのものが成り立たないからです。そこに目を付ければ、債権の一部でも回収に結びつけられる可能性があります。
また、必ずしも金銭を直接的に抑えることだけが債権回収の手段ではありません。金銭に代わる何らかの価値を持つ資産やサービスを通じて回収を進める方法もあります。取引先が持っている設備や在庫、あるいは取引先が提供可能な役務を代替手段とすることによって、間接的に回収の実効性を確保する試みが必要です。
つまり、金銭の欠如が即「回収不能」を意味するわけではなく、工夫次第でいくつもの選択肢が残されています。そこで本稿では、その中でも特に金銭以外の手法に焦点を当て、いくつかの有効な回収策について解説していきたいと思います。
保証・担保
取引先が支払困難な場合でも、保証や担保を設定することにより回収の可能性を広げることができます。まず、代表者個人の連帯保証を付与してもらう方法が考えられます。企業に資産がなくとも、代表者個人に不動産や預貯金などの財産がある場合には、そこから弁済を受けられる可能性があるからです。保証契約を通じて法人格の壁を超えて責任を負わせることは、古くから用いられてきた手法です。
また、取引先が所有する財産を担保に取る方法も有効です。在庫商品や機械設備、不動産権利など換価価値のある財産があれば、それを担保に設定し、弁済が滞った際に実際に換価することによって回収が可能になります。特に不動産担保や動産譲渡担保は、実務上も広く利用されてきました。
しかし、このような保証や担保には留意すべき制約も存在します。たとえば、中小企業が倒産する場面では、経営者保証ガイドラインに基づき、一定条件を満たした場合に代表者保証の解除が求められることがあります。債権者としても、保証が絶対的に機能するとは限らない現実を理解しておく必要があります。また、担保に取った財産も、債務者が勝手に処分してしまうリスクがあります。仮に担保権を設定していたとしても、換価の手続きには時間と費用がかかるため、必ずしもスムーズに債権回収につながるとは限りません。
したがって、保証や担保は有力な手段であるものの、万能ではありません。交渉段階からしっかりと法的効力を持つ契約を結び、状況の変化に備えて柔軟に対応できるよう準備しておくことが不可欠です。
労務の提供
金銭の支払いが困難な取引先に対しては、労務の提供を代替手段とする方法も考えられます。通常、企業間取引では代金は金銭で支払われることが前提となっていますが、必ずしも現金に限定されるわけではなく、契約次第では労務やサービスの提供で弁済することも可能です。
例えば、従業員による労務提供を代替弁済とする方法があります。たとえば、会社に損害を与えた従業員が金銭での賠償を行えない場合に、低額の時給で勤務を継続させ、その通常賃金との差額を損害賠償に充てるという手法です。ただし、このような形態は強制労働とみなされるリスクがあり、労働基準法や民法の制約を受けるため、必ず専門家の助言を得ながら慎重に進めなければなりません。
また、取引先が運輸業や倉庫業、清掃業などを営んでいる場合、自社の必要とするサービスを割安で受け、その分を債務弁済とみなすことも可能です。現物での支払いと似ていますが、サービスの供給を受ける点で異なります。特に物流や保管などの業務は他社に委託するケースが多く、こうした代替弁済は比較的導入しやすいといえるでしょう。
ただし、労務提供による弁済は、金銭回収に比べて明確な評価が難しく、のちのトラブルに発展しやすい点も見逃せません。どの程度のサービス提供で、いくらの債務が消滅したのか、契約書や覚書で詳細に定めることが必要です。こうした前提をクリアすれば、労務の提供は現実的な代替回収策として有効に機能します。
相殺
債権回収の手法の一つに「相殺」があります。これは、債権者が取引先に対して債務も有している場合に、互いの債権債務を差し引いて精算する方法です。特に取引先との間で継続的な取引関係がある場合には、この方法が現実的かつ有効に機能します。
例えば、自社が取引先から商品やサービスを購入して代金を支払う義務がある一方で、取引先が未払いの代金を抱えている場合、双方を相殺することで実質的な回収を果たせます。この仕組みを応用すれば、取引先が資金を直接持っていなくても、実務上のやり取りの中で債権を消し込むことができます。
相殺のメリットは、現金回収に比べて迅速かつ低コストである点です。裁判所を介さずとも契約関係の中で処理できるため、手続きの負担も少なく済みます。また、取引先に過度の負担をかけずに自然な形で回収が進むため、関係性を大きく損なわずに済む可能性があることも利点です。
一方で、相殺には一定の制約があります。まず、不法行為に基づく損害賠償債権と、通常の債務を相殺することは認められないケースがあるため注意が必要です。また、債権の性質によっては相殺適状に該当しない場合もあるため、事前に法的に確認することが必要です。また、取引先が倒産手続きに入ると、相殺権の行使が制限される場面もあり得ます。
このように、相殺は使い方を誤ると無効になったりトラブルを招いたりするおそれがありますが、適切に行えば非常に強力な回収手段となります。契約上の債権債務を丁寧に洗い出し、相殺が可能かどうかを判断することが、実務上重要になります。
敷金の差押えは最終手段
差し押さえるべき財産が見当たらない企業であっても、事業所の敷金という資産を保有しているケースは多いものです。自社ビルで事業を営んでいない限り、多くの企業は賃貸オフィスを利用しており、入居時には敷金を大家に預けています。この敷金は債権者にとって差押えの対象となり得る財産です。
もっとも、敷金の差押えはあくまで「最後の手段」と位置づけるべきです。なぜなら、敷金は原則として退去時に返還されるものであり、差し押さえてもすぐに資金化できるわけではありません。しかも、退去時には原状回復費用などが差し引かれるため、実際に戻ってくる金額は予想よりも大幅に少なくなることが多いのです。さらに、取引先が夜逃げ同然で退去するような事態になれば、大家が未払い賃料に充当してしまい、返還される敷金はほとんどゼロに近づきます。
加えて、敷金を差し押さえたことによって、大家がその企業の経営状態を不審に感じ、契約関係に悪影響を及ぼす可能性もあります。場合によっては、退去を促され、結果的に取引先が廃業に追い込まれるリスクすらあります。そうなれば、債権者としても継続的な取引機会を失い、長期的には不利益につながりかねません。
したがって、敷金の差押えは「確かに使えるが、慎重さを要する手段」であるといえます。強行する前に、他の方法での回収可能性を十分に検討し、それでも選択肢が残されていない場合に限って行使するのが賢明です。
まとめ
支払困難な取引先から債権を回収するのは容易ではありません。資金の乏しい企業は差押えの対象となる財産が少なく、「お金のない企業が最強」と揶揄される状況を生み出します。しかし、だからといって完全に諦める必要はなく、工夫次第で金銭以外の形で回収の道を探ることが可能です。
保証や担保を用いて代表者や資産を押さえる方法、労務やサービスの提供を受けて代替弁済とする方法、双方の債権債務を相殺する方法、さらには敷金の差押えといった手法があります。それぞれに長所と制約があり、万能ではありませんが、状況に応じて適切に組み合わせれば、回収の可能性を高められます。
重要なのは、感情的に「支払えない相手からは何も取れない」と諦めるのではなく、冷静に相手の資産や事業実態を分析し、法的に許容される範囲で最適な手法を模索する意識です。金銭以外の手段を検討することは、結果的に自社のリスク管理能力を高め、将来の債権トラブルにも備えることにつながります。
当センターでは相手の資産状況をふまえ、公認会計士の知見も活用して最も効果的な債権回収案を提案させていただきいます。下記よりお気軽にご相談ください。

当センターは、弁護士・公認会計士・中小企業診断士・CFP®・ITストラテジストなどの資格を持つセンター長・杉本智則が所属する法律事務所を中心に運営しています。他の事務所との連携ではなく、ひとつの窓口で対応できる体制を整えており、複雑な問題でも丁寧に整理しながら対応いたします。
窓口を一本化しているため、複数の専門家に繰り返し説明する必要がなく、手間や時間を省きながら、無駄のないスムーズなサポートをご提供できるのが特長です。
大阪府を拠点に、東京、神奈川、愛知、福岡など幅広い地域のご相談に対応しており、オンラインでのご相談(全世界対応)も可能です。地域に根ざした対応と、柔軟なサポート体制で、皆さまのお悩みに親身にお応えいたします。
初回相談は無料、事前予約で夜間休日の相談にも対応可能です。どうぞお気軽にご相談ください。





